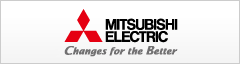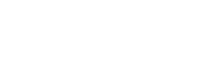甲子園ボウルの歴史
日本のアメリカンフットボールは、立教大学のポール・ラッシュ博士により1934年(昭和9年)に組織化された。当時日本に留学していた日系二世たちを中心として関東の大学でチームが結成され、戦前のチームとしては立教大、明治大、早稲田大、慶応大、法政大、日本大が関東で、関西大、同志社大、関学大が関西で創部した。
その活動は第2次世界大戦で中断し、戦後まもなく1946年(昭和21年)2月に関西、6月に関東でそれぞれ大学の連盟が結成され活動が再開される。戦前の1939、40年に、甲子園ボウルの前身とも言える東西大学の対抗戦が行われたが、戦争のため中止を余儀なくされた。
甲子園「バウル」の誕生

甲子園球場は1945年8月30日から1947年1月10日まで米軍に接収されており、その解除後に選抜中等野球が行われた。1947年(昭和22年)1月、連合軍は3月30日からの選抜中等野球大会(現センバツ高校野球大会・毎日新聞社主催)を甲子園球場で行うことを許可し、この球場を再び日本人が使用できるようになった。
この頃、大阪毎日新聞社記者の葉室鐵夫(1936年のベルリン五輪200m平泳ぎ金メダリスト・日本大OB、2005年10月30日逝去)は、甲子園ボウルの立案者である編集局長本田親男(のち社長)の指示でアメリカンフットボールの試合会場を捜していた。
東西大学王座決定戦となる試合を計画、対戦カードは、関西から前年リーグ戦優勝の同志社大、関東からはやはり復活したばかりの昨秋のリーグ優勝校・慶応大を予定。この両校は戦前から定期戦を行っていたため、大学間の連絡もスムーズだった。
毎日新聞社に先立ち、同志社大OBの三浦清が上京、慶応大と交渉するなど熱心に活動し、これに毎日新聞社が協力することとなり、葉室にそのマネージメントが回ってきた。
葉室はアメリカの大学アメリカンフットボールのビッグゲームに付けられる「ボウル・ゲーム」という言葉にこだわり、「ボウル」すなわち、おわん型のスタジアムでの試合実現を目指した。
まず阪急電鉄に西宮球場での開催を申し込んだが、阪急サイドからは西宮球技場での開催を勧められた。そこで交渉を甲子園球場に絞った。スタジアムの型へのこだわりによって生まれたのが、「甲子園ボウル」ということになる。そのころ甲子園球場のまわりにイチゴ畑が作られていたので「ストロベリー・ボウル」というネーミング案もあった。
アメリカでは開催地の特産品がボウル・ゲームの名前としてつけられることが多いということがあったからである。例えばパサディナの「ローズ・ボウル」、マイアミの「オレンジ・ボウル」などである。
ともかくも、葉室、三浦、さらに同志社大、慶応大関係者の熱意が実り、4月13日、春の中等野球(現在の高校野球)終了後に「第1回毎日甲子園バウル」行われることとなった。
この甲子園という会場を確保するために尽力したのが、葉室と同じく毎日新聞社の記者であった今村得之である。
今村はハワイ生まれの二世で、ハーバード大と慶応大で学んでいた。日系人にして初めて『リーダーズ・ダイジェスト』に記事を書いたジャーナリストとしても知られている。この今村の努力で甲子園が確保されたわけだが、第1回が春に行われたのは、同志社大の三浦が、慶応大との春の定期戦の復活を同時期に考えていたため、これを毎日新聞社の計画に組み入れるという形になったことによる。第2回大会からは、アメリカのボウル・ゲームの時期である、秋のリーグ戦終了後に開催されるようになった。
この葉室がこだわった「ボウル」という言葉だが、米語の発音は「バウル」の方が近いということでこういう表記になったという。第5回大会までこの表記が使われた。
第1回大会は、慶応大が日系二世選手らの活躍で快勝した。慶応大は、アメリカで1940年代から多く採用されていたTフォーメーションという、関西ではまだあまり紹介されていなかった攻撃隊形を使用した。当時、関西の大学フットボールでは戦前からのシングルウィング・フォーメーションという攻撃隊形が中心だったため、にわかに対応ができず45-0と大敗した。

現在のショットガンのように、ロングスナップからプレーが始まるシングルウィング・フォーメーション(協会ロゴ・マークの隊形)に慣れていた同志社大の選手にとって、ボールは守備側の選手から「見える」ものであった。それが慶応大のTフォーメーションでは、QBがセンターのすぐ後ろに位置するので、ボールの動きが守備側からは見えず戸惑ったという。Tではなく「ノートルダム・ボックス」であったという説もある。
関東の大学では日系二世や、アメリカ人コーチによってもたらされたTフォーメーションを採用しているところが多く、早稲田大や立教大のTフォーメーションに、その後甲子園ボウルに出場した関学大も戸惑うことになる。 この当時のアメリカンフットボールは、現在のような攻守に分かれた2プラトンシステムではなく、選手は攻撃も守備もこなす兼任が基本だった。ちなみにこの日の観衆は700名。入場料は大人10円、学生5円だった。慶応大の宿舎は甲子園のスタンド下にあった和室。ルールの打ち合わせは前日に行い、審判は慶応大の藤堂監督が務めるという、現在の目から見れば変則的な運営だった。
1947年(昭和22年)の秋のリーグ戦、関東は4勝1分の明治大が優勝、関西は関西大が同じく全勝でシーズンを終えた。1948年1月1日、両校が第2回甲子園ボウルで対戦した。
第2回大会はアメリカの大学ボウル・ゲームにならって元日開催となった。関西大は守備が奮起、明治大を無得点に封じ、6-0で日本一となる。この時から3年間、関西大のバックスの中心として活躍したのが羽間平安。羽間はこののち1955年の第10回大会より連続36年間、甲子園ボウルの主審の笛を吹き続けた名審判である。
ただ終戦間もない時代、年末年始の交通事情は非常に悪く、明治大の遠征が大変な強行軍となってしまったことから、甲子園ボウルの元旦開催はこの年だけで終わった。
昭和20年代(1954年まで)
昭和20年代の甲子園ボウルの出場校は、関東は慶応大からはじまり、明治大が出たあと、3年連続して慶応大が出場。そのあとはロナルド・オークス監督率いる立教大がTフォーメーションを駆使し、4回連続出場を果たしている。
関西は同志社大が第1回大会に代表となったあと、関西大が2年連続出場。その翌年からは、関学大の甲子園ボウル連続出場がスタート。この連続出場は1982年に京都大が関西リーグ優勝を果たすまで続いた。

1949年(昭和24年)、関西では関学大が、旧制中学でタッチフットボールを経験した新1年生が期待通りの活躍を見せ、秋のリーグ戦を全勝し初優勝を飾る。関東は4勝1敗で慶応大が優勝。12月18日の甲子園ボウル、関学大はダブルリバースなどの多彩な攻撃で25-7と快勝、甲子園でも初優勝をなしとげた。
翌1950年、12月10日に迎えた第5回甲子園ボウルは前年と同カード、関学大と慶応大の対戦となった。関学大が20-6で勝ち、甲子園ボウルで最初に連覇したチームとなる。その後の昭和20年代は、オークス監督にひきいられた立教大、米田満監督の指導を受けた関学大がそれぞれ2連覇している。
| ©関西アメリカンフットボール協会フットボール史研究会 | |
| 参考資料: | 「毎日甲子園ボウル50年史」毎日新聞社 |
| 「関西アメリカンフットボール史」関西アメリカンフットボール協会 | |