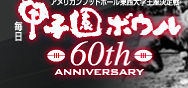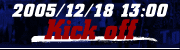|
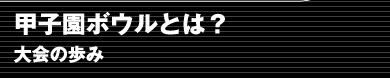 |
日本のアメリカンフットボールは、立教大学のポール・ラッシュ博士により1934年(昭和9年)に組織化された。当時日本に留学していた日系二世たちを中心として関東の大学でチームが結成され、戦前のチームとしては立教大、明治大、早稲田大、慶応大、法政大、日本大が関東で、関西大、同志社大、関学大が関西で創部した。 |

甲子園球場は1945年8月30日から1947年1月10日まで米軍に接収されており、その解除後に選抜中等野球が行われた。1947年(昭和22年)1月、連合軍は3月30日からの選抜中等野球大会(現センバツ高校野球大会・毎日新聞社主催)を甲子園球場で行うことを許可し、この球場を再び日本人が使用できるようになった。 |

現在のショットガンのように、ロングスナップからプレーが始まるシングルウィング・フォーメーション(協会ロゴ・マークの隊形)に慣れていた同志社大の選手にとって、ボールは守備側の選手から「見える」ものであった。それが慶応大のTフォーメーションでは、QBがセンターのすぐ後ろに位置するので、ボールの動きが守備側からは見えず戸惑ったという。Tではなく「ノートルダム・ボックス」であったという説もある。 |
|
この当時のアメリカンフットボールは、現在のような攻守に分かれた2プラトンシステムではなく、選手は攻撃も守備もこなす兼任が基本だった。ちなみにこの日の観衆は700名。入場料は大人10円、学生5円だった。慶応大の宿舎は甲子園のスタンド下にあった和室。ルールの打ち合わせは前日に行い、審判は慶応大の藤堂監督が務めるという、現在の目から見れば変則的な運営だった。 |
|
昭和20年代の甲子園ボウルの出場校は、関東は慶応大からはじまり、明治大が出たあと、3年連続して慶応大が出場。そのあとはロナルド・オークス監督率いる立教大がTフォーメーションを駆使し、4回連続出場を果たしている。 |

1949年(昭和24年)、関西では関学大が、旧制中学でタッチフットボールを経験した新1年生が期待通りの活躍を見せ、秋のリーグ戦を全勝し初優勝を飾る。関東は4勝1敗で慶応大が優勝。12月18日の甲子園ボウル、関学大はダブルリバースなどの多彩な攻撃で25−7と快勝、甲子園でも初優勝をなしとげた。 |
©関西アメリカンフットボール協会フットボール史研究会 |
|
参考資料: |
「毎日甲子園ボウル50年史」毎日新聞社 |