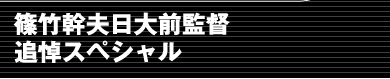* * * * *
京大の怪物QB東海辰弥が卒業した翌年から日大の甲子園3連覇(ライスボウルも史上初の3連覇)が始まる。いわゆる日大「最後」の黄金期である。<第43回大会/88年〜第45回大会/90年>
WR梶山は、高い技術と優れた身体能力、それに加えて強靱な精神力で、近年の日大黄金期を代表するレシーバーである。
89年、90年と2年連続の関東学生リーディングレシーバーを獲得、90年には、レシーバーとしては最初のミルズ杯を受賞した。球際の強さと絶妙のポジションニング、ここ一番で発揮する驚異的な集中力で、当時のマスコミから「ゴッドハンド」と呼ばれた。
* * * * *
【腐ったスイカが引き留めたゴッドハンド】
−−まず日大に入学した動機というのはなんだったのでしょう?
高校時代(追手門高校)は、ほとんど秋のシーズン1回戦で負けていたような学校でしたが、やっぱり自分は1番になりたかったのですね。自分がやっているスポーツではトッププレーヤーになりたいし、オールジャパンにも入りたい。そう考えたときに一番手っ取り早いのは、そういう状況が整っていて、そのチームでがんばればそうなれるところに入ろうと、それで日大に入学した。
そこのレギュラーになったら、ジャパンのレギュラーだし、そこでがんばって優勝できたら日本一。誰も文句言わないだろうと。周りからしてみたら無謀だと思われるようなことだったけれども、まずそこに行こうと決めたわけです。
−−実際に入部した時の感想はどうでしたか?
入部当時は練習できなかった、させてもらえない。基礎的な練習はやる、でも、肝心なチームプレーになったら、1軍と2軍しか出来ないわけですよ。練習は試合形式で進むから練習には参加できない。1年生で見込みのある選手だけがそこに加わるわけ。でもそれは限られていて、何十人もの順番があるのです。
だからチャンスを与えてもらうために、わずかな練習でも先輩の技術を盗み取るしかない。それで夏ぐらいにはもう無理かなと思って、やめようかと思ったぐらいでした。
−−それでもやめずに続いたわけですよね。
当時は合宿所で寝泊まりしていましたから、夏休みになると何日か地元に帰してくれるのですね。一度大阪に戻って合宿所に帰ってきたときに、ベッドがスイカで埋まっていた。チームにスイカの差し入れがあって置き場所がなかったから、留守の間、僕のベッドが空いていたのでそこに置いていた、スイカを30個ぐらい。
僕が帰ったから「どけるわ、ゴメンな」って、動かしたときにスイカの下の方が腐っていて、スイカがベッドの上で爆発した。
腐ったスイカって、それはもの凄い異臭でね・・・。しばらく自分のベッドに近寄れないわけですよ。これって、ものすごく理不尽な話だと思うでしょ。人権もへったくれもない(笑)。いまの若い子だったら、キレまくって帰るとこですよね。
|